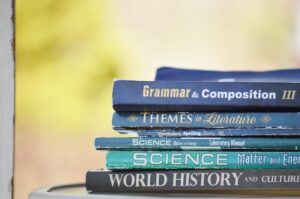「GTDでのタスク管理って何?」「GTDでのタスク管理って難しそう」と警戒している方もいると思います。
GTDは、タスクを管理して生産性をあげる方法のことです。脳内でタスクを管理しているだけでも脳の容量をとり、知らない間に生産性を下げています。GTDの考え方は、とてもシンプルですが、慣れるまでに時間がかかる方法です。
この記事では、GTDについてやGTDでタスク管理を行うメリット、GTDの具体的な手順を紹介します。GTDでのタスク管理に興味がある方は参考にしてください。
GTDとは
GTDとは、アメリカの生産性向上コンサルタントであるデビッド・アレン氏が提唱したタスク管理の手法です。「Getting Things Done」の頭文字をとった略語であり、直訳すると「物事を成し遂げる」になります。
タイムマネジメントの技術としてビジネスシーンで多く活用されている整理術です。プライベートにも使える技術のため人気があり活用されています。
GTDでタスク管理を行うメリット3つ
GTDでタスク管理を行うとどんなメリットがあるのでしょうか?メリットを知ることで、日常生活にも取り入れやすくなります。
生産性が上がる
GTDでタスク管理を行うことにより、生産性の向上が望めるでしょう。
1度、タスクを頭の中から出すことにより、自分が抱えているタスクの量や内容を客観的に見ることができます。
また、頭の中でタスクを管理するだけでも脳にはとても負担がかかるため、頭の中から出すだけでも目の前のタスクに集中しやすくなります。
精神的なストレスが減らせる
タスクを頭の中から出すことで、精神的なストレスを減らせるでしょう。
何かしている時に他のことが気になり、集中できなかったことはあると思います。「あの期限いつまでだったかな?」「お昼は何を食べようかな?」など、目の前のことに集中できていないと、全てのタスクが中途半端になります。
また、タスクを把握しておくことやタスクをこなせていないことに焦りを感じ、精神的なストレスが貯まりやすくなるでしょう。GTDは、そんな脳内の負担を減らし、ストレスを軽減してくれます。
あらゆるタスクの管理ができる
「タスク」と聞くと仕事のニュアンスが強いかもしれませんが、日常生活でも使えるのがGTDのタスク管理です。
GTDの使い方を覚えると、ビジネスやプライベートとシーンに関係なく使えるため、とても便利な方法といえます。
GTDでタスク管理を行う5つのステップ
GTDでタスク管理を行うには、5つのステップがあります。
- ステップ1:把握する
- ステップ2:見極める
- ステップ3:整理する
- ステップ4:更新する
- ステップ5:選択する
1つ1つ理解して実際に行ってみましょう。実践することで早く身につきます。
ステップ1:把握する
まずは、自分が今抱えているタスクを把握するために、全て頭の中から出す作業です。
ビジネスやプライベートなこと、完了したものや未着手のものまでタスクの大小に限らず、気になるタスクを全て書き出してください。タスクとして明確に決まっていなくても頭の中で気になるものは全てです。例えば「仕事の進捗状況」や「休日にできる趣味」なども気になっているのであれば書き出しておきましょう。
全てを書き出す事ができればいいですが、書いている時点では忘れているタスクもあります。そういったタスクを思い出させてくれるのがトリガーリストです。以下が、トリガーリストの1例です。
- やりかけのプロジェクトは?
- 着手すべきプロジェクトは?
- 考慮すべきプロジェクトは?
- 約束していることは?
これらの質問を仕事やプライベートのことに落とし込んでみると、忘れていた事や気にかけていなかったタスクまで思い起こしてくれます。
書きだすのは、手帳やノート、アプリやスマートフォンのメモ機能など何でもかまいません。気になる事が出てきた時に対応できるよう持ち運びができるツールの方がいいでしょう。ご自身が管理しやすいツールで行うことをおすすめします。
ステップ2:見極める
「見極める」は、書き出したタスクに対して「何をしたらいいか」を考えるステップです。このステップでの判断は以下のような流れになります。
- まず、書き出したタスクを見て「そのタスクは何かする必要があるのか」を考える
- 次に「そのタスクは行動を起こす必要があるのか」を考える
- 行動する必要がある場合「求めている結果」と「次に取るべき具体的な行動」を考える
- 「次に取るべき具体的な行動」を考えたら、それを「今すぐやるのか」「誰かに任せるのか」「あとでやるのか」に分ける
例えば「PCが動かない」というタスクを、上記の流れにあてはめて考えてみましょう。
1として、日常生活に支障をきたすため、何かする必要があると考えます。2も行動を起こす必要があると考えるでしょう。3で「求めている結果」は「PCが正常に動作する」で、「次に取るべき行動」は「PCに詳しい人に聞く」や「PC会社に修理の依頼をする」などが挙げられます。そして、4でどうするのかを判断する流れです。
ちなみに、4は「2分以内にできるかどうか」と「自分で行うのか他人に任せるか」の2軸で考えると判断しやすくなります。「PCの修理を依頼する」は、2分以内に自分で行えることです。そう判断したら、その場で修理依頼を行いましょう。タスクが1つ片付きます。
ステップ3:整理する
ステップ3は「見極める」で意味づけされたタスクを自分で振り分ける作業です。「見極める」際にそのタスクがもつ意味をしっかりと理解できているとスムーズに整理が行えます。
整理の仕方として、仕事やプライベート、職場や自宅など環境や状況に応じて分けると、整理がしやすく分かりやすいです。職場でないと行えないタスクなのか、相手がいないとできないタスクなのかなど、タスクを行う状況を想定して整理しましょう。
ステップ4:更新する
日々、変わるタスクに対応してGTDでのタスクの内容や優先度も変化していくものです。そのため、GTDでのタスクを定期的に見直して、最新の状態に更新していく必要があります。
更新するためにおすすめの方法が、週ごとにレビューする方法です。できればレビューを行う日時や場所を決めておいて、定期的に行いましょう。レビューをすることで、終ったタスクや新しく生まれたタスクが更新されると、優先度の判断もつきやすくなります。
ステップ5:選択する
最後は、行うタスクを選択し実行する段階です。
実行する時になって、行動に迷う時もあると思います。迷った時には、以下で紹介する適切な行動を選ぶ4つの基準を参考にしてください。
- そのときの状況
- 使える時間
- 使えるエネルギー
- 優先度
「そのときの状況」で行えるタスクは何かを考えましょう。当たり前ですが、PCがない状況では、PCが必要なタスクは行えません。「使える時間」が5分しかないのに、20分もかかるタスクも行えません。また「使えるエネルギー」も同様に、集中力が必要なタスクに疲れている時や体調が悪い時には向いていないでしょう。
最後の「優先度」は、上記の3つを考慮して絞られたタスクの中から何を優先して行うかを選ぶものです。
例えば、会社にいてPCもあり、30分も時間の余裕があって疲れていない状態で、どのタスクを選びますか?選択肢が多くて悩むかもしれません。そういった時に優先度が高いタスクを選びましょう。
参考:『全⾯改訂版 はじめてのGTDストレスフリーの整理術』デビッド・アレン 著、⽥⼝元 監訳/2015 年/⼆⾒書房
GTDのタスク管理で効率を上げよう!
ここまで、GTDのタスク管理を行うことのメリットや手順を紹介してきました。GTDは脳内の負担を減らし、タスクに集中するための整理術です。慣れるまでに時間はかかるかもしれませんが、GTDを継続することで生産性や効率は上がります。GTDを実践しながら身につけていきましょう。
タスクを行う方法はさまざまあります。その1つが「habitee」です。Zoomで集まったメンバーと25分間という限られた状況で習慣化したいことやタスクを行います。1人では続かないことも他者がいると続けられるかもしれません。興味がある方は、1度使ってみることをおすすめします。